人口DNA断片製造ディスラプターかつ、高成長企業のツイストバイオサイエンス(TWST, TWIST BIOSCIENCES)について分析します。
参考記事: 米国株IPOスクリーニング、高成長かつ綺麗な加速感ある10銘柄
※上の記事にあるように、過去4四半期連続>+30%yoyで売上が伸びており、直近のQの売上成長は大きく加速しています。
今回の記事の要点は以下になります。
- 強みはオンリーワン的な製造技術。製品自体はオンリーワンではない。
- 圧倒的な低コストで好きな配列のDNA断片を人工的に作れる。
- DNA断片への需要はNGS(次世代DNAシーケンサー)がけん引してきた。
- さらに合成生物学や、がんの診断、ゲノム編集などでDNA断片への需要が伸びそう。
- 抗体医薬などに向けた創薬プラットフォーム事業構築も目指す。
- DNA断片を使った記憶媒体という夢もある。

それではさらに深堀していきますね。
DNA断片とは?
TWST社はDNA断片を圧倒的な低コストで作れる技術を持っています。
DNAはACTG…といった4種類のアルファベット(塩基配列)が延々と繰り返されたものです。
DNA断片はそれが途中で切れたものを指します。
任意の塩基配列で作れるのがポイントで、これが製品になります。

そのような断片を誰が使うのか?という疑問が湧いてきますが、のちほど書いていきます。
次に、同社の一番の特徴である製造技術です。
DNA断片の製造技術
同社の製造技術は元々存在していた製造方法を極限までミニチュアサイズにしたものです。
下図の右側が彼らのプラットフォームです。
下図の左側を半導体の技術によりミニチュア化したもの。

DNAの断片は従来、図の左側にあるように、ウェルプレートと呼ばれる96の穴が開いたプレートを使って製造されていました。
最終的に目指す配列をAACCTTとします。
一つの穴ではAA、次の穴でCC、三つ目の穴でTTという断片を人工合成し、後でつなげれば、
AACCTTになります。
このように、一つ一つの穴で小さなDNA断片を合成し、それを個々で増殖、最後に全部繋げて完成というやり方です。

実際は、断片の前後の配列を工夫がされており、最後に混ぜたときに目的の配列の長い断片になるように設計されてます。
問題は、膨大な試薬を消費することと、ウェルプレート一枚あたりたった一つの遺伝子しか作れないことです。
同社のプラットフォームであれば、9600の遺伝子を作ることができるとしています。
効率は9600倍。
ただ、技術的な問題が一つあり、長い配列を作ることが難しいようです。
なお図の中央にあるマイクロアレイ方式は、ウェルプレート方式よりも効率がいいですが、効率は96倍程度としています。
小さな断片の合成が終わったあと、くっつけるために一回チップから外す処理が必要になり、非効率であるとのこと。
創業者はアジレント出身
創業者兼CEOの Emily Leproust 氏は、アジレント出身であり、アジレント時代の技術が、同社の技術の土台になっているようです。
推察の域になってしまいますが、アジレントはもともとHPからスピンオフされた会社で、プリンター事業に代表されるように液体の吹き付け技術を持っています。
同社の製造工程を見てみると、微細な穴一つ一つに試薬などを設置する必要があり、細かく液体を吹き付ける技術をつかっているのではないかと思います。
ちなみに同社は技術を転用したとしてアジレントから訴訟を受けていましたが、金銭による解決となったようです。
DNA断片は何に使うのか?
ここから、同社の製品であるDNAの断片が何に使われるのか見ていきます。
NGSで使われてきた
NGS(次世代DNAシーケンサー)によってDNAを読むという需要が同社の製品の需要をけん引します。
遺伝子の配列を読む際に、特定の配列だけを濃縮し、それ以外の情報は捨てたほうが効率的ですよね?
DNAの断片はこの特定の配列を濃縮するターゲットエンリッチメントに使用されています。
メチル化解析
同社の製品はDNAのメチル化解析にも使われます。
メチル化とはDNAの配列の一部が変性することですが、変性することにより遺伝子の発現が抑えられることなどが分かっています。
がんの発生を抑制する遺伝子の発現がメチル化により抑制され、がんの原因になっていることが、わかっています。
そのため、がんの診断分野でメチル化したDNAを調べること、いわゆるメチル化解析に注目が集まっています(メチル化解析の他に、ミューテーション(変異)を調べるものもあります)。
超巨大化が見込まれるがん早期診断市場での先端企業について深堀
メチル化が起きやすい遺伝子上の特定配列を濃縮するのにもDNA断片は使われます。
以下がメチル化解析のワークフロー(ケンブリッジ大学のスライド参照)です。
①血しょうを採取し、②バイサルファイト処理を施す、③ターゲット配列のみを濃縮(同社製品が使われる場所)、④NGSにより解析

なお下の図は、同じくケンブリッジ大学の資料ですが、TWST社の宣伝かのごとく他社製品との比較を行っています。
コストに関しては口頭でコメントしていましたが、1/3ほどだそうです。
コストは明らかに安く、イールドも高いということでしょう。


まとめると、がんの診断により、NGSに需要が集まり、それにより同社製品への需要が高まるということですね。
合成生物学
合成生物学の領域においても同社の製品は使われます。
合成生物学の領域では、酵母菌など原始的な生物にDNAを組み込むことで、様々な物質を作らせることがさかんに試みられています。
例えば、日本でも有名なスパイバー社の人口クモの糸が該当します。
その他、医薬品の原料としてすでに実用化されているものがあります。
目的となるタンパク質をコードするDNA断片を酵母菌などに組み込むことが必要で、その断片の提供に同社等の製品が使われています。
なお、この業界ではGingkoという大手の会社が存在し、TWSTは同社向けの売上が2020年度売上のうち12%となっています。
DNAをハードディスクのように利用?
DNAはデジタルデータの記録媒体として活用できないかというプロジェクトが進行しています。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/dna-5.php
同社はマイクロソフト、ウエスタンデジタル、イルミナなどと共にこのプロジェクトに参画しています。
記録媒体として使用するためのハードルの一つに、DNAの合成をいかに安く済ませるかという問題があり、ローコストプレイヤーの同社が選ばれたということであると考えられます。
DNA断片販売以外のビジネス
DNA販売以外のビジネスとして、創薬の分野にも進出しようとしています。
具体的には、抗体医薬の分野です。
抗体医薬品の候補となる抗体を設計する技術確立を目指しています。
抗体自体はタンパク質で、タンパク質はDNAにコードされています。
そのため、そのDNAの一部を変化させることで、目的となる抗原により作用する抗体を設計できる可能性があります。
同社のテクノロジーを使えば、任意の配列を持つDNAをローコストで設計できるため、これにより候補物質のライブラリーを抱えることができるというわけです。
実際10Kによると、コロナウイルスに対する抗体を75種類、同社のプラットフォームで同定したとのことです。
コロナウイルスが流行り出してすぐの3月時点での成果であるそうです。
この抗体に関してはパートナーへの販売を見込むとしていますが、現時点でのステータスは不明。

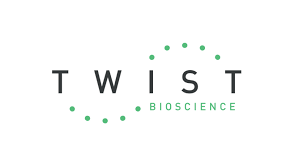
コメント